セントラルヒーティングで家まるごと省エネ!プロが教える驚きの暖房術

セントラルヒーティングは建物全体を暖めてくれる暖房システムであり、24時間つけっぱなしが基本です。
そのため「光熱費が高くなるのでは?」「デメリットが多そう」と考える方も少なくありません。
そこで、この記事ではセントラルヒーティングの仕組みや特徴、導入時の費用、セントラルヒーティングの良さ、無駄と思われがちな要因など気になるところを解説します。
セントラルヒーティングの導入に悩まれている方はぜひ参考にしてください。
セントラルヒーティングの基本的な仕組み
セントラルヒーティングとは、全館空調の一種であり、一つの熱源で建物全体を暖める暖房システムです。
具体例としては、ボイラーで電気やガス、石油などを燃やして温水や熱風を発生させ、建物内の各部屋に張り巡らせた循環パイプを通して各部屋のパネルヒーター(放熱器)を暖めます。
セントラルヒーティングの種類は「温水式」と「温風式」の2つです。
セントラルヒーティングの種類
| 【温水式セントラルヒーティング】 一般的にセントラルヒーティングといえば温水式を指します。温水式セントラルヒーティングは、熱源で温めた温水を循環パイプを通じて各部屋のパネルヒーターへ届け、建物内を暖めます。 【温風式セントラルヒーティング】 温風式のセントラルヒーティングはファンヒーターのようなもので温風を発生させ、循環パイプから部屋へ届けて建物内を暖めます。 |
セントラルヒーティングの制御システムには、ボイラーとパネルヒーターに搭載されたサーモスタットバルブや室温を感知するセンサーがあります。
制御システムの例
| 【サーモスタットバルブ】 パネルヒーターに搭載されている目盛り付きのバルブで、室温を感知して温水の量を調節する 【室温を感知するセンサー】 室温を感知して、ボイラーやパネルヒーターの温度を制御する |
セントラルヒーティングは石油ストーブのように子どもやペットが火傷する心配もなく、火を使わないため、火災や一酸化炭素中毒のリスクが低いことも利点と言えるでしょう。
熱源の種類と特徴
セントラルヒーティングの熱源は「電気」「ガス」「石油」の3種類です。
それぞれのメリット・デメリットをまとめました。
| 熱源 | メリット | デメリット |
| 電気 | ・24時間つけっぱなしにできる | ・光熱費が上がりやすい ・立ち上がりに時間がかかる |
| ガス | ・都市ガスを利用すると料金を抑えられる ・立ち上がりが早く、エネルギー消費量が小さい | ・つけっぱなしだと料金が上がりやすい |
| 石油 | ・自宅にストックできて災害時にも役立つ ・立ち上がりが早く、エネルギー消費量が小さい | ・つけっぱなしだと料金が上がりやすい |
電気が熱源だと24時間つけっぱなしの方が節約できますが、ガスや石油は長時間の外出や就寝時には止めた方が節約になるでしょう。
電気・ガス・石油それぞれの初期費用は、ボイラー・循環パイプ・パネルヒーターの中を流れる不凍液などを合わせると100万〜150万円です。
電気・ガス・石油の維持費としてかかるコストの例を以下にまとめました。
| ・電気:世帯人数4人・延床面積120㎡・設定温度23℃・暖房24時間連続でオール電化を使った場合、年間約65万円の電気代がかかる ・ガス:世帯人数4人・延床面積120㎡・設定温度23℃・暖房24時間連続で都市ガスを使った場合、年間約33万円の電気・ガス代がかかる ・石油:令和7年2月現在の石油価格1リットル126.8円、北海道苫小牧市のセントラルヒーティング年間石油消費量が1927.5リットルで算出すると年間約24.4万円の石油代がかかる |
北海道では、電力会社やガス会社によって、セントラルヒーティングにぴったりのプランを提案してくれるので、プランの見直しをすると維持費の節約につながるかもしれません。
参照:北海道ガス「コレモを使えば、電気代・ガス代がおトクに!」より
参考:経済産業省 資源エネルギー庁「石油製品価格調査」より
参考:苫小牧市「家庭の燃料等の消費節約実態調査」PDF4ページより
システムの制御方法
セントラルヒーティングはパネルヒーターについている目盛り(サーモスタットバルブ)と、ボイラーリモコンで温度レベルの設定をして、室温を制御しています。
サーモスタットバルブによる室温の制御とは、お部屋の上限温度を設定し、丁度いい室温になったら暖めるのをやめて室温をキープする機能です。
ボイラーリモコンで設定する温度は、お部屋の温度ではなく、パネルヒーターに流す不凍液・温風の温度なので注意しましょう。
ボイラーリモコンの温度が低すぎるとお部屋全体が暖まるのに時間がかかり、光熱費も上がりやすくなります。北海道の一般的な冬場の設定温度目安50℃〜60℃に設定してから少しずつ調整し、快適な気温を見つけるのが良いでしょう。
最新のセントラルヒーティングには遠隔操作機能が搭載されており、自宅を留守にしていても、スマートフォンからヒーターのオン・オフ切り替え、設定温度の変更ができます。
スマートフォンによる遠隔操作機能は、家に帰ったら暖かい状態をキープできたり、消し忘れたら外出中でもオフにできたりするところが魅力と言えるでしょう。
導入時の費用と投資回収の目安
セントラルヒーティング導入にかかる初期費用は「ボイラー本体価格+パネルヒーター代×台数+工事費」で算出できます。
導入時に必要な機材とそれぞれの相場から内訳をまとめました。
初期費用の内訳
| 導入費用相場 | 100万〜150万円 | |
| 導入費用相場の内訳 | ボイラー本体価格 | 40万〜60万円 |
| パネルヒーター代(一般的な戸建て住宅で7枚設置の場合) | 35万〜70万円 | |
| 工事費 | 20万〜25万円 | |
導入費用に加えて気になるのが、24時間稼働になるセントラルヒーティングの年間光熱費ではないでしょうか。
年間光熱費の例と光熱費削減の例
セントラルヒーティングの光熱費目安は公表されていないため、セントラルヒーティングの導入率が高い北海道電力におけるオール電化家庭を参考に年間光熱費を紹介します。
4人暮らし・オール電化・延床面積120㎡・設定温度23度・暖房24時間稼働を例にした試算では、年間電気代65万円となっており、季節によって変動はありますが、1ヶ月あたりの電気代はおよそ5.4万円です。
このようにセントラルヒーティングの熱源を電気にすると電気代がかさみますが、エネルギー源を少ないガス量で効率よく運転する「ガスボイラー(コレモ+エコジョーズ)」にした場合の節約例を紹介します。
4人暮らし・コレモ+エコジョーズ・延床面積120㎡設定温度23度・暖房24時間稼働を例にした試算で、年間光熱費33万円で1ヶ月あたりの電気代はおよそ2.7万円です。
比較すると年間32万円の光熱費削減が可能で、セントラルヒーティング導入費用150万円の先行投資金を約5年ほどで回収できる計算になります。
参照:北海道ガス株式会社「どのくらいお得になるの?オール電化」より
参照:「光熱費がこんなにお得に!」試算条件はこちらより
省エネルギー設備導入による補助金制度
経済産業省「給湯省エネ2025事業」より、それぞれの補助額に該当する対象モデルを導入すると、内容に応じて1台あたり5万円からの補助金が支給されます。
補助金対象になる台数の上限は、戸建て住宅であれば2台まで支給可能です。
参照:経済産業省 資源エネルギー庁「給湯省エネ2025事業(令和6年度補正予算「高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金」について)」より
地域別の導入コスト比較
セントラルヒーティングは全国的に主流なわけではなく、北海道などの寒冷地でのみ採用されており、北海道では実に7割〜8割の新築戸建て住宅が導入しています。
北海道以外の地域では「給湯暖房熱源機」と呼ばれる給湯と床暖房がメインの温水暖房が多く、導入費用は戸建て住宅で6畳床暖房付きとすると50万〜70万円が相場とされています。
一方で、北海道でセントラルヒーティングを導入すると100万〜150万円と高額ですが、暖房のエネルギー消費量の多い北海道では、室内の温度を一定に保てるように暖房負荷を考慮しなくてはなりません。
北海道の暖房負荷は、冬季の厳しい寒さに対応して快適な住環境を実現するために重要であり、24時間稼働のセントラルヒーティングは暖房効率の低下を防いでいるのです。
冷暖房両用システムの可能性
ここ数年で住宅における冷暖房システムに大きな変化が起きています。
今までは冷暖房の方法として冬はセントラルヒーティングや床暖房、夏はエアコンを利用するなど、複数の機器を組み合わせるのが一般的でした。
しかし、近年では地球温暖化の原因となる温室効果ガスをゼロにする取り組みが加速しており、一つの機器で住宅の冷暖房を担う全館空調システムの導入が増加傾向にあります。
【冷暖房を担う全館空調システムの具体例】
| ・ヒートポンプ式(ダクト式):空気や水などの熱を汲み上げて移動させるヒートポンプ式熱源機で、空気を除湿・温度調節するシステム ・エアコン方式:高気密・高断熱住宅で少ない台数のエアコン使用する方式 ・床下冷暖房方式:床下空間を利用して各部屋に設置した吹き出し口へ冷暖気を送る |
上記のシステムは導入費用が120万〜300万円と高くなりますが、年間を通して一定の温度を保てて、エネルギー消費量の少なさから維持費を抑えられるのが特徴です。
全館空調システムの将来性は、高断熱住宅の普及や技術の活用により、市場規模の拡大や利便性の向上などが期待されています。
セントラルヒーティング導入は無駄が増えるって本当?
セントラルヒーティングは北海道などの寒冷地では一般的な暖房システムとなっており、新築戸建住宅の70〜80%が採用しています。
しかし、セントラルヒーティングには暖房の機能しかなく、冷房機能は備えていません。夏に冷房が必須となる温暖地ではエアコンの設置も必要になり、初期設置費用が高額なことやランニングコスト、メンテナンス費用などを考慮すると余分な出費が増える可能性はあるといえるでしょう。
この記事では、セントラルヒーティングの導入が本当に無駄なのかどうかを検証していきます。
セントラルヒーティングの良さとは?
家全体を暖められる
セントラルヒーティングはボイラーで熱を作り、循環パイプを巡り各部屋に設置された放熱器(パネルヒーター)によって家全体を暖めます。
各部屋に暖房器具(エアコンや石油ストーブなど)を設置するよりも効率がよく、どの部屋もほぼ均一の温度を保てるため家中どこにいても快適に過ごせます。また、設定した温度以上になることもありません。 家全体の温度が均一になるため、急激な温度変化により起こるとされるヒートショックの予防効果も期待できます。
室内が乾燥しづらく空気がクリーンに保てる
セントラルヒーティングはエアコンのようにファンから温風を出すのではなく、パネルヒーターを伝って部屋を暖める暖房装置です。
温風を発生させないため空気の乾燥を防ぎ、チリやホコリなどのアレルギー物質が舞うことも無いため空気がクリーンな状態を保てます。
火を使わないため安全性が高い
セントラルヒーティングは熱源で温めた温水をパネルヒーターへ送り出し暖めるという仕組み。ファンヒーターや石油ストーブのように家の中で直接火をつけたり灯油を補充したりする必要がないので、火災のリスクは低いでしょう。
不完全燃焼することもなく、一酸化炭素や二酸化炭素も発生しないため、換気が気になることもありません。また、パネルヒーターの表面温度は約40℃〜70℃程度ですので、小さなお子様やペットがいても大きな火傷に繋がりにくくなっています。
熱源の交換ができる
セントラルヒーティングの熱源は、電気・ガス・石油など複数から選択が可能です。
今後、温暖化への対策として熱源を変える必要が出た場合にも大きな工事は必要なく、ボイラーの変更のみで対応可能。故障した時や熱源を他の種類に変えたい時に、パネルヒーターはそのままで熱源だけを交換できるという点は、セントラルヒーティングのメリットの一つといえるでしょう。
セントラルヒーティングが「無駄」と思われがちな要因
定期的な不凍液の交換が必要
パネルヒーターの中を流れる不凍液(暖房用温水)は徐々に劣化して量も減るため、3〜4年を目安に交換が必要です。交換費用は戸建住宅で5~7万円前後かかります。
不凍液には凍結防止・サビ抑制といった効果がありますが、約2年で効果が低下していきます。劣化した不凍液を使い続ける配管内をサビなどの不純物が循環し、詰まりや腐食、ボイラー内のポンプに負担をあたえて暖房効率が落ちてしまいます。
以上のような理由で不凍液は定期的な交換が必要なのですが、1回の費用が大きい分、無駄だと感じてしまうこともあるでしょう。
パネルヒーターのお手入れ
パネルヒーターはエアコンと違いフィルターの掃除が不要ですが、表面・本体の隙間や壁との隙間にはゴミやホコリがたまりやすく汚れが生じます。
ホコリが付着していると放熱効果を弱めてしまうため、定期的な手入れが必要。水洗いができないので、柔らかい乾いた布などで表面を拭き取り、隙間などは柔らかいエアダスターや細い棒に乾いた布を巻いてホコリを取ってください。
また、パネルヒーターからの液漏れなどがないかの確認も必要です。
ボイラーの保守点検
セントラルヒーティングは長時間稼働し続けるため、使用期間につれてボイラーや周辺機器の消耗や劣化が進んでいきます。ボイラーの寿命は10〜15年前後と言われていますが、点検をおろそかにすると寿命が短くなるリスクが高まります。
費用は1~2万円程度かかりますが、経年劣化、使用頻度の多さに加えてボイラーの穴あき・油漏れ・不凍液漏れなども故障の原因となるため、定期的な保守点検を行いましょう。
保守点検の頻度としては、1年に1回行っておくのがおすすめです。
セントラルヒーティングを無駄なく活用するために
つけっぱなしで使用する
セントラルヒーティングはすぐに暖まる仕組みではないため、オフにして冷めた水を再度温めるまでには大きなエネルギーと時間が必要になります。頻繁にオンオフを切り替えると効率が悪くなるため、シーズン中は24時間つけっぱなしにするほうが経済的です。
シーズンオフになるまで稼働させ続け、就寝時や外出の際は設定温度を低めにすることで効率的に活用できます。
家全体の温度を均一にする
各部屋で好みの温度に調整できますが、部屋ごとの設定温度がバラバラだと多くのエネルギーが必要になるため、なるべく均一にしましょう。
また、部屋ごとに設定温度が違うと結露の原因になるだけでなく、対流によりホコリが舞ってしまい空気の汚れにもなります。
北海道などの寒冷地では温度差により窓ガラスやサッシなどに結露が発生することがありますが、カビやダニ、住宅の建材を傷めてしまう原因となる結露はなるべく押さえられるように対策しましょう。
高気密・高断熱設計にする
セントラルヒーティングを導入したとしても、建物の気密性が低いと冷たい空気が入り、断熱性が低いと暖気が逃げて暖房の効果が弱まってしまいます。
セントラルヒーティングで効率よく家を温めるには、家を高気密・高断熱設計にすることが肝要。新築だけでなく後付けの場合でも、セントラルヒーティングを導入する際には気密性や断熱性をできるだけ高めるようにしましょう。
まとめ
セントラルヒーティングは1つの熱源で建物全体を暖めるシステムであり、日本では主に北海道で普及しています。
家中暖められるので、温度差がなく北海道の厳しい寒さの中でも快適に過ごせて、火事や一酸化炭素中毒のリスクが低いところやメンテナンスが簡単なところが魅力です。
しかし、住宅の広さやライフスタイルによって変わりますが、光熱費は年間24万〜65万円が目安であり、ランニングコストが高くなりやすい特性もあります。
光熱費が上がりやすいデメリットの対策として、エネルギー源が電気の場合は24時間つけっぱなし、ガス・石油はこまめに消すと光熱費を節約できるでしょう。
また、高気密・高断熱設計の住宅であれば暖気が逃げにくくなり、セントラルヒーティングで効率よく家を暖められます。
セントラルヒーティングの維持費用を抑えるためにも、上記のような光熱費を節約できる使い方や高気密・高断熱設計の住宅を参考に導入を検討してみてください。
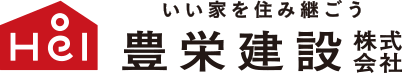


 お客様相談室
お客様相談室 資料請求
資料請求


 見学ご予約
見学ご予約


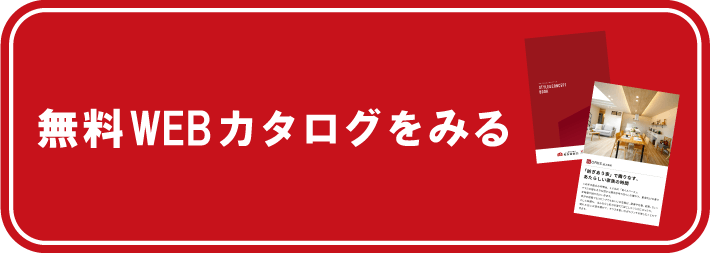
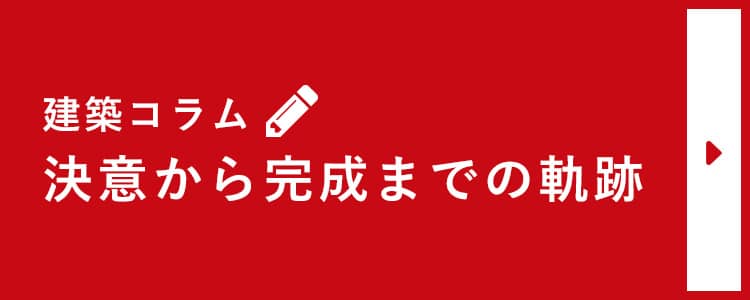







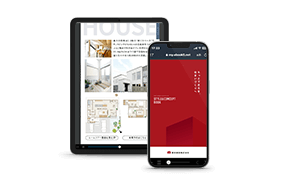




 Facebook
Facebook LINE
LINE Instagram
Instagram YouTube
YouTube

