用途地域とは?全13種類の特徴と制限を徹底解説!

家を建てる土地を探していると、よく目にするのが「用途地域」という言葉ではないでしょうか。
用途地域は物件の環境や利便性を知るために活用できる便利な情報ですが「用途地域ってどういうもの?」「13種類もあるから違いがわからない」と悩む方も少なくありません。
この記事では、土地探しで用途地域を知っておくべき理由、全13種類ある用途地域それぞれの特徴と選ぶときのポイントを解説します。
これから土地探しを検討する方は、ぜひ参考にしてください。
用途地域とは?基本的な仕組みをわかりやすく解説
用途地域とは、都市計画法に基づいて土地を用途ごとに区分し、建築できる建物の種類や規模、高さなどを定めた制度です。
都市計画法は、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため、都市計画に関する事項を決めた法律で、都市計画事業などを規定しています。
用途地域の目的は以下の通りです。
・住居の環境を保護する
・業務の利便性を高める
・望ましい市街地へ誘導する
たとえば、家の近くに工場や商業施設、ビルが入り乱れた状態の土地は住みづらく、景観もよくありません。お互いの利便性や生活環境を守ることを目的として土地の用途を定めているのが用途地域です。
用途地域は13種類のエリアに分類されており、種類ごとに建築できる建物の用途や延床面積などの建築規制が制定されています。
用途地域は、市区町村が作成する都市計画図に、種類ごとに異なった色を用いて表示され、用途地域が設定されていないエリアには色が塗られていません。
暮らしの快適さを守るゾーニングの仕組み
用途地域ゾーニングとは、都市計画において、地域を用途や機能によって区別・区画し、その土地利用を定めることです。
家づくりや物件探しの際に用途地域まで確認しておくと、都市の発展の仕方が分かり、自分のライフスタイルに合った地域かどうか確認できます。
たとえば、大型の商業施設を建設できない地域では閑静な住宅街が形成でき、高層ビルを建設できる地域では買い物やアクセスに便利な街並みが形成されると予想できるのです。
また、住居専用地域に工場の建設申請があっても排除が可能になるなど、法律を背景として用途地域の環境を守れる有力な手段にもなっています。
用途地域から街の役割を知り、自分の住みたい街のイメージとマッチしているのかどうかを把握できるでしょう。
最新の13種類の区分と特徴
用途地域は5年に一度見直されており、都市部の農地の住宅地化などで用途地域の種類が新たに追加されて13種類になりました。
ここでは最新の13種類の用途地域のそれぞれの特徴と制限事項を表にしています。
| 分類 | 用途地域 | 制限事項 |
| 住宅系 | 第一種低層住居専用地域 | 低層住宅のための地域です。 小規模なお店や事務所を兼ねた住宅、小中学校などが建てられます。 |
| 第二種低層住居専用地域 | 主に低層住宅のための地域です。 小中学校や150㎡までの一定のお店などが建てられます。 |
|
| 第一種中高層住居専用地域 | 中高層住宅のための地域です。 病院、大学、500㎡までの一定のお店などが建てられます。 |
|
| 第二種中高層住居専用地域 | 中高層住宅のための地域です。 病院、大学などのほか、1500㎡までの一定のお店や事務所など必要な利便施設が建てられます。 |
|
| 第一種住居地域 | 住居の環境を守るための地域です。 3,000㎡までの店舗、事務所、ホテルなどが建てられます。 |
|
| 第二種住居地域 | 住居の環境を守るための地域です。 店舗、事務所、ホテル、カラオケボックスなどが建てられます。 |
|
| 準住居地域 | 道路の沿道において、自動車関連施設などの立地と、これと調和した住居の環境を保護するための地域です。 | |
| 田園住居地域 | 農業と調和した低層住宅を守るための地域です。 住居に加え、農産物の直売所などが建てられます。 |
|
| 商業系 | 近隣商業地域 | 周りの住民が日用品の買い物などをするための地域です。 住宅や店舗のほかに小規模の工場を建てられます。 |
| 商業地域 | 銀行、映画館、飲食店、百貨店などが集まる地域です。 住宅や小規模の工場も建てられます。 |
|
| 工業系 | 準工業地域 | 主に軽工業の工場やサービス施設などが立地する地域です。 危険性、環境悪化が大きい工場のほかは、ほとんど建てられます。 |
| 工業地域 | どんな工場でも建てられる地域です。 住宅やお店は建てられますが、学校、病院、ホテルなどは建てられません。 |
|
| 工業専用地域 | 工場のための地域です。 どんな工場でも建てられますが、住宅、お店、学校、ホテルなどは建てられません。 |
同じ「低層住居専用地域」でも、第一種よりも第二種の方が住宅以外の建物を建てられるといった違いから周辺環境がわかり、住み始めてからの暮らしも見えやすくなります。
さらに、用途地域は、地域別に敷地面積に対する建築面積の割合を示す「建ぺい率」と、延床面積の割合を示す「容積率」の比率が定められています。
用途地域に対する建ぺい率と容積率を一覧表にしました。
| 用途地域 | 建ぺい率(%) | 容積率(%) |
| 第一種低層住居専用地域 | 30、40、50、60 | 50、60、80、100、150、200 |
| 第二種低層住居専用地域 | ||
| 第一種中高層住居専用地域 | 100、150、200、300、400、500 | |
| 第二種中高層住居専用地域 | ||
| 第一種住居地域 | 50、60、80 | |
| 第二種住居地域 | ||
| 準住居地域 | ||
| 田園住居地域 | 30、40、50、60 | 50、60、80、100、150、200 |
| 近隣商業地域 | 60、80 | 100、150、200、300、400、500 |
| 商業地域 | 80 | 200、300、400、500、600、700、800、900、1,000、1,200、1,300 |
| 準工業地域 | 50、60、80 | 100、150、200、300、400、500 |
| 工業地域 | 50、60 | 100、150、200、300、400 |
| 工業専用地域 | 30、40、50、60 |
参照:国土交通省「みらいに向けたまちづくりのために」PDF5ページより
これらの数字は大きいほど建設面積の割合が大きいと表しています。
そのため、「第一種低層住居専用地域」の建ぺい率30〜60%、容積率50〜200%よりも「第一種住居地域」の建ぺい率50〜80%、容積率100〜500%の方が広い面積の家を建てられるとわかります。
このように、用途地域によって「建てられる家の大きさ、高さ」「周辺の環境」が異なるので、事前に調べておくと家づくりや物件探しのヒントになるでしょう。
用途地域の3つの分類とは?住居・商業・工業の特徴を比較
用途地域を住居・商業・工場の3つに分けたとき、それぞれどのような特徴があるのでしょうか。
主な役割と特徴は以下の通りです。
| 【住居系】 13地域あるうち8地域あるのが「住居系」で、住環境が優先されている用途地域 この8地域に指定された地域には大きな工場、商業施設は建てられない 【商業系】 13地域あるうち2地域が「商業系」で、主に大勢の住民が買い物や遊び場として利用できる商業施設が建てられる地域 【工場系】 13地域あるうち3地域が「工場系」で、広い敷地と大量の電力の確保など、主に工場の利便性を高める地域 |
住居の環境を守るため制限が多いのが住居系地域であり、商業系と工業系は発展を重視している地域とわかります。
快適な暮らしを実現する「住居系」の魅力
住居系の用途地域は、居住用建物を建てるのに適したエリアであり、住居の環境を守るために規制が厳しく設定されています。
住居系用途地域には「原則として商業系・工業系の建物が建築できない制限のある地域」から「中規模の商業系・工業系の建物と住居系建物が混在しても良い地域」もあり、範囲が広いのが特徴です。
たとえば、低層住居専用地域では住宅地の環境を最優先した建築制限があり、住宅以外の建築物は公共施設や医療・福祉関係の施設に限られていて、快適な暮らしを守れるように用途地域が細分化されています。
住居系用途地域は適切な住環境の保護、住宅の確保ができるからこそ暮らしやすさに繋がっているのです。
便利で活気のある「商業系」の特色
商業系用途地域とは、商業施設の建築を優先的に想定している地域です。
商業系用途地域には店舗やオフィス、商業施設などに対する制限が比較的ゆるいのが特徴で、床面積の制限なく建築できます。
たとえばターミナル駅の周辺、都道府県の中心街、繁華街や歓楽街が商業系用途地域に当てはまり、利便性の高い地域を形成して地域活性化させる役割を担っています。
住居も建てられますが、商業施設が優先されるので、商業施設が隣接する可能性や人の出入りが多く比較的賑やかな地域であると理解しておかなくてはなりません。
一方で、商業系用途地域に住宅を建てると、交通アクセスの良さ、資産価値の下がりにくさがメリットにもなります。
モノづくりを支える「工業系」の役割
工業系用途地域は、工場や倉庫などの建設を可能にする地域で、地域経済を支える重要な役割を担っています。
「危険物を取り扱う業種で住居に適さない地域」と「危険物はなく騒音・振動を発生させにくい工業は住宅地と混合建築しても良い地域」で分類されているのが特徴です。
たとえば、工業専用地域では住宅・学校・病院・ホテルなどの建築も許されておらず、住むことができない地域として定められています。
工業系用途地域は工業専用地域以外であれば居住可能ですが、大型車両の交通量や騒音・振動など、生活に大きな影響を与える可能性があるかもしれません。
土地選びで工業系用途地域を検討する際は、内容を詳細に把握しておきましょう。
13種類の用途地域一覧と特徴を徹底解説
13種類に分かれた用途地域それぞれの特徴を表にしました。
| 用途地域 | 特徴 |
| 第一種低層住居専用地域 | ・主に戸建て住宅を指し、建ぺい率や容積率の制限も厳しい ・建物の高さは10mまたは12mと高さ制限が設けられており、高い建物が建てられない ・戸建て住宅でも設計内容によっては3階建てが建てられない可能性もある ・事務所や店舗は住居と兼任している場合のみに建てられる ・アパートや低層マンション、学校(幼稚園から高校まで)などの建築は認められている |
| 第二種低層住居専用地域 | ・主に戸建て住宅をメインとしているが、一種との違いは店舗の床面積(第一種の最大が50㎡に対し、第二種は150㎡まで)の店舗が建てられる ・コンビニや飲食店などの建設も認められており、低層でも利便性が高い |
| 第一種中高層住居専用地域 | ・高さ制限がないため、戸建て以外の分譲マンションも建設可能 ・住宅の他に教育機関(幼稚園から大学まで)や図書館、飲食店、病院などの建設が認められている ・オフィスビルの建設は認められていない ・低層住居専用地域よりもスーパーや学校などが増えて、利便性が高い |
| 第二種中高層住居専用地域 | ・第一種との違いは、店舗の床面積の広さと中規模な事業所が建設できるところ ・床面積1,500㎡までの、やや大きなスーパーマーケットなど多様な建物が建てられる |
| 第一種住居地域 | ・住居がメインで、駅周辺の地域が多く、商業施設が立ち並ぶ ・建物の高さに制限がなく、大型マンションやオフィス、宿泊施設、病院などが建てられる ・パチンコ店やカラオケ、風俗店は認められていない |
| 第二種住居地域 | ・第一種との違いは、商業施設の大きさと多さ ・床面積が10,000㎡までで、ショッピングセンターやボーリング場など大型商業施設が建てられる ・パチンコ店やカラオケを含める遊戯施設も認められている |
| 準住居地域 | ・国道、幹線道路沿いでマンション住宅がメイン ・ショッピングモールや映画館、倉庫、駐車場も多い |
| 田園住居地域 | ・2018年に新たに追加された地域であり、住宅のメインは低層住宅 ・第一種低層住居専用地域に農家が加わったイメージで、直売所やレストラン、農機具用の倉庫が建設可能 ・教育機関や病院、神社なども建設が認められている |
| 近隣商業地域 | ・マンションがメインの居住地域 ・ドラッグストアやホームセンターなど日用品を購入できるお店が多く立ち並ぶ ・住居系地域よりは賑やかなエリア |
| 商業地域 | ・大きなターミナル駅の周辺に広がる商業地域 ・飲食店や百貨店、映画館、夜のお店などあらゆる施設の建設が認められている ・利便性も高く、住居も建てられるが、商業施設が優先されるエリアであり、騒音や治安については安心しにくい |
| 準工業地域 | ・軽工業を始めとした、さまざまな工場を建てられる地域 ・住居を建てられる地域でもあり、環境や人体に悪影響を及ぼす工場の建設は認められていない ・工場以外に学校や宿泊施設、病院の建設が認められている |
| 工業地域 | ・準工業地域では認められていない工場を建てられるエリア ・湾岸エリアや工場跡地に多い ・住居はタワーマンションがメインで戸建ては少ない ・大型車両が頻繁に出入りする |
| 工業専用地域 | ・住居を建てることができないエリア ・鉄工場や石油コンビナートをはじめとした、あらゆる工場が建てられている ・工業専用の地域であり、住居だけでなく病院や商業施設の建設も認められていない |
用途地域は設定されている役割によって、住環境が大きく変わります。
静かな住宅街を望むなら制限の厳しい地域、利便性を求めるなら制限がゆるい地域や商業地域を選ぶなど自分の生活に合った環境を選び、より良い暮らしを目指しましょう。
各用途地域の特性と選び方のポイント
住む地域を選ぶ際に「用途地域の選択基準がわからない」と悩む方も少なくありません。
そこで、どのような特性があり、どのような人におすすめなのか、用途地域の選択基準を表にまとめました。
| 用途地域 | 特性 | おすすめな人 |
| 第一種低層住居専用地域 | 閑静な住宅地 | ・都会の喧騒から離れた生活を送りたい人 ・駅から少し離れているので、車をよく利用する人 ・広い庭を持ちたい人 |
| 第二種低層住居専用地域 | 閑静な住宅地だが利便性も高い | ・コンビニなど小さなお店が近くにほしい人 ・静かさと利便性の両方を求める人 |
| 第一種中高層住居専用地域 | 3階建て以上の分譲マンションもあるが、比較的静か | ・比較的静かな環境で、3階建て以上の分譲マンションを検討している人 ・買い物の利便性を優先する人 |
| 第二種中高層住居専用地域 | 生活に必要なサービスが比較的そろっている | ・マンションに住みたい人 ・周辺に中規模の買い物施設が欲しい人 |
| 第一種住居地域 | 駅から近く、夜道も明るい | ・マンションに住みたい人 ・静かな住宅地よりも、駅の近さや商業施設の近さを求める人 |
| 第二種住居地域 | 住環境としては賑やか | ・遊べるところも欲しい人 ・小さな繁華街に住みたい人 |
| 準住居地域 | 幹線道路沿いが多く、住環境としては最も賑やかで、自動車移動に便利 | ・車移動を主としている人 ・車でさまざまな用途の店舗を利用したい人 |
| 田園住居地域 | 田畑が広がる、静かで落ち着いた環境 | ・農業と一体化した市街地を形成していない地域に住みたい人 |
| 近隣商業地域 | 多少の騒がしさはあるが、住居系としては利便性が高い | ・生活に必要な商業施設の多さを求める人 ・高層マンションに住みたい人 |
| 商業地域 | ターミナル駅周辺のエリアで、交通の利便性も高い | ・高層マンションに住みたい人 ・交通アクセスの良さを重視する人 ・ショッピングエリアが生活圏内に欲しい人 |
| 準工業地域 | 住居系・商業系・工業系すべての建物が乱立する日影規制により日当たりの良いエリアで、戸建て住宅も多い | ・地域内の工場に勤めている人 ・日中は外出が多いなどの理由で周辺の騒がしさが気にならない人 ・日当たりの良さを求める人 |
| 工業地域 | 湾岸エリアに多く、高層マンションからの眺望が良い | ・高層マンションに住みたい人 ・高層階から海や街を眺めて生活したい人 |
| 工業専用地域 | 住居の建築ができない | 住むことができないため、向いている人はいません |
新居を構えるエリアとして工業系は避けたいと考える方も多いですが、工業系の用途地域の中でも準工業地域は商業や住居が発展して選ばれる場合もあります。
用途地域から住まいを選ぶなら、以下のポイントを意識して自分に合った環境を選びましょう。
用途地域から住まいを選ぶ際のポイント
| ☑︎必要な施設やサービスの有無 ☑︎通勤や通学の便 ☑︎買い物のしやすさ ☑︎安全性 ☑︎子どもの遊び場や自然環境 |
住まいを選ぶときは用途地域の特性を理解し、実際に足を運ぶなどして現地を確認しましょう。
用途地域の調べ方と確認のポイント
用途地域は自治体のホームページから検索したり、国土交通省の国土数値情報「用途地域データ」をダウンロードしたりする方法で調べられます。
特定の用途地域を調べたいときは、以下のポイントに注意しなくてはなりません。
用途地域を確認するときの注意点
| ・対象の敷地が2つ以上の用途面積をまたがる場合、敷地の過半数を超える部分の用途地域の制限を受ける ・用途地域が定められていないエリアも存在する ・用途地域や都市計画道路の境界にあたる地域は都市計画課の窓口で確認する |
都市計画道路は、国・県・市の都市像から検討して決めている整備計画です。都市計画道路の予定地は、将来的に道路になる可能性もあり、立ち退きや分割が必要になるかもしれません。
住みたいエリアが将来的にどのような都市計画になっていくのかを、用途地域を活用して適切に把握しましょう。
参照:国土交通省「国土数値情報ダウンロードサイト」用途地域データより
自治体サイトでの確認手順
用途地域を自治体のサイトで確認する方法は以下の通りです。
用途地域の確認手順
| ①市区町村のホームページで公開されている用途地域を確認する ②「調べたい地域名+用途地域」で検索する ③色分けされた地図から、エリアごとの用途地域を確認する |
用途地域の色分けは自治体によって定義が異なる場合もありますが、おおむね見方は変わりません。白色で表示されている地域は「用途地域がない」と意味しています。
住まいを検討中の方は住みたいエリアの用途地域をチェックしましょう。
都市計画図の読み方のコツ
都市計画図は地方公共団体が作成する行政区内の都市計画の内容を示した地図です。
都市計画図の入手方法は、前述の用途地域の確認手順同様で「調べたい地域名+用途地域」もしくは「調べたい地域名+都市計画図」で検索すると表示されます。
都市計画図を読む時のポイントをまとめました。
都市計画図のポイント
| ・縮尺2,500分の1以上の平面図で表されている ・地域によって異なり、自治体ごとに作成される ・誰でも閲覧可能で、紙媒体・電子データ・インターネットなど自治体によってさまざな形で提供されている ・都市計画法に基づいて決定された都市計画の内容を示した図面である ・都市計画区域内は計画的に都市計画しようとするエリアであり、道路や橋などのインフラ整備が進みやすい |
都市計画図からわかることは以下の3つです。
・用途地域や地区計画などの土地利用規制
・都市計画が決定された道路や公園などの施設
・土地区画整理事業の市街地再開発事業の区域
都市計画図の情報を活用すると、街づくりの計画がよくわかり、住んでいる地域やこれから購入予定の土地の情報を調べるのに役立つでしょう。
物件購入前の環境チェックリスト
どんなに理想通りの物件や土地だったとしても、周辺環境に不満があると住み始めてから困るかもしれません。
では、周辺環境のチェックポイントとして、どのような点が挙げられるでしょうか。
周辺環境を見る際のチェックリストを紹介します。
| 周辺環境 | 確認ポイント |
| 交通の便利さ | ・最寄り駅やバス停までの距離 ・電車とバスの本数 ・始発と終電の時間 ・職場や学校につくまでにかかる時間 ・交通機関の種類 ・通勤時間帯の道路混雑状況 |
| 生活の便利さ | ・スーパーやコンビニ、ホームセンターまでの距離 ・商品の品揃え ・医療機関までの距離 ・医療機関の診察時間 |
| 環境の良し悪し | ・騒音や振動、においに問題ないか ・日当たりや風通しは十分か |
| 治安の良し悪し | ・繁華街と近いか ・深夜営業のお店はあるか ・夜間の人通りの多さ ・空き地と空き家の数 ・交番やコンビニはあるか |
| 災害に関するもの | ・地盤の弱さ ・大雨の時に浸水する可能性 ・地盤沈下や液状化のリスク ・避難場所までの距離 |
| 子育てに関するもの | ・学校や保育園の数と距離 ・同年代のファミリー層が周辺にいるか ・公園や図書館など、子ども向けの遊び場や施設があるか |
周辺環境をチェックするには、実際に現地を歩いてみるのがおすすめです。
平日と土日では周辺環境の雰囲気が変わります。できれば平日と土日、同じ曜日でも時間帯を変えて訪れ、周辺の治安についても調査しましょう。
土地調査で見落としがちな注意点
土地調査で周辺環境以外に見落としやすいポイントを以下にまとめました。
【水はけ】
・水はけが悪いと、住宅内の湿度が高くなり、カビやダニの発生率が高まる
・地盤に水が溜まりやすくなり、地盤沈下の恐れがある
【地盤】
・地盤が弱いと、建物の傾きやひび割れが起こりやすくなる
・近くに河川や海がある地域、地下水位が高い地域、盛土・埋め立てによる造成地は地盤が弱い傾向がある
【法律上の制限】
・用途地域の高さ制限や敷地面積の制限
・建物の形や性能への制限
・接道義務を果たしているか
・隣地との境界が明確か
災害が多い日本では、住む地域の災害リスクを知る必要があります。
自治体が掲載しているハザードマップか、国土交通省の「ハザードマップポータルサイト」で場所を入力して災害リスクを確認しておくと、万が一の時にも役立ちます。
接道義務とは、幅4m以上の道路に2m以上土地が接していなければ、建物を建築できないルールです。
道路幅が4m未満の場合、道路の中心線から2m後退したところを道路境界線とみなして接道義務を果たす「セットバック」が適用され、そのぶん土地が削られるといったデメリットもあると理解しておきましょう。
よくある質問
用途地域について、よくある質問には次のようなものがあります。
Q.用途地域の境界線はどうやって調べる?
A.用途地域境界線の明示を希望される場合、自治体の窓口に必要な申請書と測量図を持っていくと、土地の正確な位置や形状を調べてくれます。
各自治体によって持っていく書類と資料が異なるため、自治体の都市計画課窓口やホームページで直接確認しましょう。
Q.用途地域が定められていない地域は家を建てられる?
A.用途地域が定められていない土地でも、原則として家を建てられます。
| 用途地域が定められていない土地の例 ・都市計画区域内で区域分けがされていない「無指定区域」 ・都市計画が定められていない「都市計画区域外」 |
ただし、未開発の場所では、水道・ガス・電気などのインフラ整備が整っておらず、交通の利便性も望めません。自由度は高いですが、家を建てる際は注意しましょう。
Q.用途地域は変更できる?
A.用途地域は自治体が定めており、個人都合の変更はできませんが、以下の条件を満たしていると建築基準法で決められた用途以外の建物を建てられます。
| 用途地域を変更できるケース ・特定行政庁が許可した ・都道府県知事の許可を得た |
しかし、用途地域の変更手順として建築審査会の同意を得なければならず、時間と費用がかかります。手間を省きたい方は建築家に相談や依頼するのも一案です。
用途地域制度の目的は?
用途地域制度は、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、住居環境の保護や業務の利便性向上を目的として設定されています。
居住エリアが騒音や環境問題に悩まされず快適に生活できているのは、無秩序な建物の建築を防いで環境を保護している用途地域制度のおかげと言えるでしょう。
用途地域はすべての土地に定められているわけではなく、市街化が見込まれる都市計画区域を対象としていて、おおむね5年に一度、全国一斉に見直されています。
また、住みたいエリアの用途地域を調べると、利便性の有無や周辺環境がわかり、家づくりや物件探しをする方の助けにもなっているのです。
住宅建築が制限される地域は?
住宅の建築が制限される地域は、工業専用地域、市街化調整区域、風致地区などがあります。
住宅の建築が制限される地域
| 【工業専用地域】 工場が集まったコンビナートや工業団地など、住宅の建設が認められていない地域 【市街化調整区域】 環境保全のために市街化を抑制しなければならない区域で、原則として住宅や商業施設などの建物を建築できない 【風致地区】 自然美の維持・保存を目的として創設された地域で、建物の建築や樹木の伐採に一定の制限が加えられる 【近隣商業地域】 都市計画法では、建築物が密集した火災危険率の高い市街地において「準防火地域」を指定し、火災の危険を防除する建築制限を定めている。 |
建築制限の理由は、環境の景観保護、火災の危険防止、都市開発を抑えるといった目的で規定されています。
家づくりのご相談は”豊栄建設”へ
札幌市にある住宅建築会社「豊栄建設」では、高断熱・高気密な家づくりや、地震に強い家づくりに取り組んでおり、安全性能や快適性能に高い評価を得ています。
豊栄建設の住宅は、柱や梁に接合金具を使用した「メタルジョイント工法」や、床下地合板を2倍にした「根太レス工法」を採用し、震度7の地震にも耐えられる機能性を兼ね備えているのが特徴です。
さらに、万が一の備えとして、お引き渡しの日から20年間不動沈下しない地盤品質を保証する「地盤品質保証」や、雨水の侵入を防止する部分の10年保証「瑕疵(かし)保証」があります。
豊栄建設は、第三者機関による厳しい施工チェックをもとに品質でお応えしており、住んでからも安心できる家づくりを実現しているのです。
地震に強い家や長期保証の家を検討している方は、ぜひ豊栄建設にご相談ください。
まとめ
用途地域は、人が多く集まる市街化区域において、安心・快適に暮らせるように土地利用の用途から建築制限を決めたものです。
全13種類のうち8種類が住宅を建築できる「住居系」用途地域で、住居系のエリア内は戸建て住宅を構えるのに適した環境が手に入るでしょう。
利便性を求める方は商業施設が多い「商業系」用途地域、眺望の良さを重視したい方は「工業系」用途地域と、このように住みたい環境イメージで決めるのも一案です。
用途地域はインターネットで「調べたい地域名+用途地域」と検索すると調べられます。
住みたい地域を見つけたら、用途地域の情報を調べたり実際に歩いたりして周辺環境の良し悪しを見極め、より良い環境の家づくりや物件探しに役立てましょう。
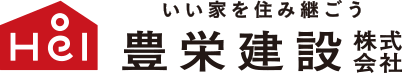


 お客様相談室
お客様相談室 資料請求
資料請求


 見学ご予約
見学ご予約


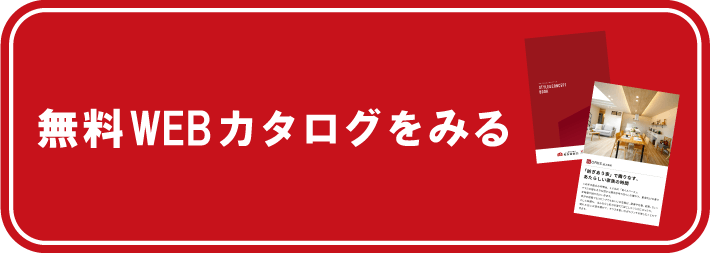
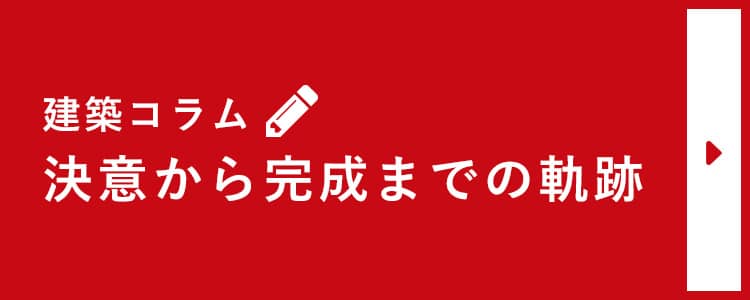







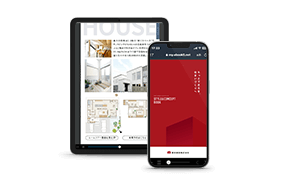




 Facebook
Facebook LINE
LINE Instagram
Instagram YouTube
YouTube

