【2025年版】ローコスト住宅とは?メリット・デメリットや失敗しない選び方を紹介

ローコスト住宅は低価格でありながら理想のマイホームを建てられるのが魅力的ですが、気になるのは住宅の「品質」ではないでしょうか。
実際にローコスト住宅を検討してみると「どんなデメリットがあるのか」「選び方の基準がわからない」と悩む方も少なくありません。
そこで、この記事ではローコスト住宅がなぜ低価格で提供されているのか、メリット・デメリット、失敗しない選び方を紹介します。
これからローコスト住宅を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
ローコスト住宅の特徴とメリット・デメリット
ローコスト住宅とは、一般的な注文住宅と比べて低価格で建てられる住宅であり、坪単価にすると30万〜50万円ほどで、1,000万円台の建築が可能な住宅を指します。
建築材料や設備の大量購入、設計の合理化、プランとデザインを限定した「規格型」の住宅にするなど家づくりの工程でコストダウンを図り、低価格を実現しているのが特徴です。
費用を抑えて家を建てられたり、契約から引き渡しまでの期間が短くスムーズに引越しできたり、リフォームしやすかったりする点はローコスト住宅のメリットと言えるでしょう。
一方、ローコスト住宅のデメリットは、以下のような点が考えられます。
・自由設計の注文住宅に比べ、間取りやデザインの自由度が少ない
・設備や住宅性能のグレードが低い
・変更時の追加オプション料金が高い
・国や自治体の補助金制度を利用しにくい
ローコスト住宅を選ぶ際は、自分や家族の生活スタイルを考慮し、ローコスト住宅の特徴を理解したうえで、最適な住宅を選択しましょう。
特徴とターゲット層
ローコスト住宅は建築費用を抑えるため、さまざまな工夫が凝らされているのが特徴です。
たとえば、建築会社が材料や部品を大量に調達することで通常よりも仕入れ価格を下げ、材料費を削減して、その分低価格での提供を実現しています。
さらに、ローコスト住宅は建物の形状や間取りが統一されており、シンプルで作業工程が少ないので、人件費や建築費を削減して家づくりが可能です。
ローコスト住宅のメインターゲットは「価格は抑えたいが、こだわりも叶えたい20代〜30代の住宅一次取得層」や「ある程度早い期間で家を建て替える予定の人」です。
20代〜30代の住宅一次取得層とは、初めて住宅を取得する20代から30代の世帯主を指します。
財務省統計局の調査によると、29歳以下2人以上世帯の持ち家率35.2%(2023年度)と過去最高を記録しており、今は3人に1人以上が持ち家を保有しています。
近年の物価高などの厳しい社会背景を捉え、賃貸よりも自由な生活環境を求める若年層のニーズに応えているのがローコスト住宅です。
その他には、将来売ることを考え、あえてシンプルなデザインと間取りのローコスト住宅を選択する方もいます。
参照:財務省統計局「家計調査〈世帯分布〉二人以上の世帯」Excel閲覧用より
3つのメリット
ローコスト住宅のメリットとして以下の3つが挙げられます。
坪単価が30万〜50万円と低価格
住宅ローンを取り扱う住宅金融支援機構の「2023年度フラット35融資利用者調査」より、
注文住宅の平均坪単価は、全国で約75万円(建築費×0.7÷延床面積)です。
これに対して、ローコスト住宅は坪単価30万〜50万円で建てられます。
たとえば30坪の住宅を建てる場合、ローコスト住宅で坪単価45万円なら1,350万円、注文住宅で坪単価70万円になると2100万円になり、ローコスト住宅とは750万円の差額があります。
建物にかかる費用を1,000万円代に抑えられると、趣味や子育てなどにお金を活用できて余裕が生まれるでしょう。
参照:住宅金融支援機構「2023年度フラット35融資利用者調査」PDF19ページより
建築期間が短い
ローコスト住宅の着工から完成までの期間は約3ヶ月間となり、建築期間が短いところもメリットです。
ローコスト住宅は間取り・外壁の種類・キッチン・トイレ・風呂の設備があらかじめ決まっていて、工場で事前に建築材料を加工しておくなど建築方法もパターン化されています。
そのため、現場での作業時間が短くなり、フルオーダーの注文住宅に比べると建築期間が短くスムーズになるのです。
ローコスト住宅は「打ち合わせを行う時間が取れない方」や「できるだけ早く家を建てたいと考える方」にも向いています。
住宅ローンの借り入れ金額を抑えられる
前述したようにローコスト住宅は坪単価が30万〜50万円と低価格であり、一般的な坪数の住宅を建てたとしても建物の価格は1,000万円代に抑えられます。
通常の注文住宅よりも少ない借り入れ金額になると、住宅ローンが組みやすく、月々の返済負担額が軽減されて家計にも余裕が生まれます。
また、住宅ローンの負担軽減によってリフォームや建て替えに対するハードルも低くなり、ライフステージの変化に合わせて選択もしやすいでしょう。
4つのリスク要因
ローコスト住宅はメリットだけでなく、デメリットとされる点もあります。
購入を検討している方は、以下の4つのリスク要因も理解しておきましょう。
気密性・断熱性が低い
ローコスト住宅は、断熱性・気密性の低い材料を使用してコスト削減をするケースがあります。
断熱性・気密性が低いと夏場は暑く、冬は寒い室内環境になり、温度を調整する冷暖房の光熱費が高くつくかもしれません。
費用を抑えて快適に暮らすには、日当たりや風通しの良い土地や間取りを選ぶなど、夏の暑さと冬の寒さを和らげる工夫が必要です。
メンテナンスの手間や費用がかかる
通常の注文住宅でもローコスト住宅でも、時間が経過すると、メンテナンスが必要になるところは変わりません。
しかし、ローコスト住宅の標準設備はグレードが低く設定されており、耐久性が低い素材が使用されていると、メンテナンスの頻度も費用も高くなります。
経年劣化による主なメンテナンス箇所は以下の5種類です。
・外壁塗装と防水加工
・屋根の塗装と防食加工
・ベランダやバルコニーの塗装
・基礎部分と配管のシロアリ防止加工
・給湯器の部品交換
ローコスト住宅は、初期費用だけでなくランニングコストやメンテナンスの手間などを考慮して家づくりを検討しましょう。
遮音性が低い
遮音性とは、室外から室内へ侵入する音や、室内から室外へ漏れる音をどれくらい防音できるかを表す性能を指します。
ローコスト住宅は最低限の性能を備えていますが、高性能住宅と比べると遮音性が低くなる場合があります。
ローコスト住宅の遮音性を高めるには、気密性を高めたり窓を二重にしたりすると、近隣への音漏れを気にせず音楽や映画鑑賞を楽しめるでしょう。
施工が雑になる
ローコスト住宅は工事期間を短くし、経験の浅い職人を採用してコスト削減する建築会社も存在します。
工事の施工や住宅性能に悪影響が及ぶと、住宅の寿命が短くなる可能性があります。
建物の安全を確保する建築基準法を満たしているかどうかなど、コストパフォーマンスの高さだけでなく建築会社そのものを丁寧に選びましょう。
重視すべきポイント
ローコスト住宅を選ぶときは、エネルギー効率を重視して断熱材や設備を選ぶと、光熱費や住宅購入後のメンテナンス費を削減できます。
ローコスト住宅におけるエネルギー効率とは、少ないエネルギーで快適な環境を維持できる住宅の性能です。
エネルギー効率の高い住宅の例として、次のようなものがあります。
・断熱材を壁・屋根・床に施工して断熱性能を高める
・隙間を減らして空気の出入りを少なくし、気密性を高める
・少ないエネルギーで効率よくお湯を沸かす給湯器を採用する
・太陽光パネルを設置して光エネルギーを電気に変換する
・夏は遮熱対策をして冷房の負荷を軽減する
・冬は太陽光を取り込んで暖房効果を高める
上記のようなエネルギー効率の高い住宅では、光熱費の削減や住み心地の向上が期待できるでしょう。
成功事例からのヒント
これまでに多くのローコスト住宅を担当してきた「豊栄建設」より、ローコスト住宅購入に成功した方の体験談をご紹介します。
| 【お家時間が充実するNYブルックリンスタイルの住まい】 重視したのは収納力。 以前の住まいでは、調理器具の収納場所が少なく、雑然とした雰囲気になりストレスを感じていたが、今では収納スペースにスッキリ収まり、調味料や食器が隠せるようになった。 さらに、ひと目でどこに何が入っているか残りはどれくらいかがわかるので、無駄な買い物が減り、1ヶ月の食費を減らせた。 こだわりたいところは徹底してこだわれて、不要なものは省けるのでコストをコントロールできた。 |
引用:豊栄建設HP「お家時間が充実するNYブルックリンスタイルの住まい」より
| 【夫婦ふたりで第二の人生を謳歌する平屋建て】 以前の住まいはグラスウール断熱材を使用していたが、経年変化で断熱機能が低下し、とても寒かった。 今回はさまざまな住宅メーカーのパンフレットを取り寄せて断熱構造を検討し、リクシルと共同開発されたウレタン断熱パネルに惹かれ、もっとも優れていると感じた豊栄建設を選んだ。 さらに、外気の影響を受けにくい基礎断熱工法や、熱交換システムにより暖房効率が良く、平均最高気温12℃の4月でも暖房が不要なほど暖かい。 |
引用:豊栄建設HP「夫婦ふたりで第二の人生を謳歌する平屋建て」より
ローコスト住宅の成功事例のヒントとしては、次のようなものがあります。
・資金計画を立てる
・標準仕様を細かく確認して不要なオプションを追加しない
・複数の住宅メーカーで住宅性能を比較する
・ローコスト住宅を建てた実績のある住宅メーカーを選ぶ
ローコスト住宅の購入を成功させる為には、無駄な費用を省き、こだわりたい部分に予算を回すのがポイントです。
ローコスト住宅の価格相場と理由
ローコストといっても、実際の購入価格には差があります。
たとえば最低限のラインが坪単価45万円、延床面積30坪だとすると、以下の計算になります。
| 建築工事費1,350万円 本体工事費945万〜1,080万円(総費用の70〜80%) +付帯工事費202.5万〜270万円(総費用の15〜20%) +諸費用135万〜202.5万円(建築費の10〜20%) =総額1,282.5万〜1,552.5万円 |
ローコスト住宅の建物に関わる費用の目安は、総額1,000万円代後半から2,000万円代前半が一般的な価格相場と言えるでしょう。
加えて、間取りや設備、仕上げにこだわる場合はその費用と土地代がかかります。
土地代は地域によって大きく差があります。住む予定の土地代を事前に調べ、土地代を合わせた総額で住宅を検討しましょう。
価格相場
価格相場は、各地域によって異なります。
ここではフラット35を取り扱う住宅金融支援機構の「2023年度フラット35融資利用者調査」を基に、注文住宅の地域別建物面積(坪数)の価格相場を表にまとめました。
注文住宅の建物面積(坪数)の価格相場
| 地域 | 平均建物面積(坪数) | 平均坪単価 | 建物面積の価格相場 |
| 全国 | 119.5㎡(36.1坪) | 74.8万円 | 2,700万円 |
| 首都圏 | 120.4㎡(36.4坪) | 80.5万円 | 2,930万円 |
| 近畿圏 | 123.2㎡(37.2坪) | 77.9万円 | 2,897万円 |
| 東海圏 | 121.0㎡(36.6坪) | 74.4万円 | 2,723万円 |
| その他地域 | 118.0㎡(35.6坪) | 71.2万円 | 2,534万円 |
参照:住宅金融支援機構「2023年度フラット35融資利用者調査」PDF19ページより
・平均坪単価は平均建設費×0.7÷平均建物面積(坪数)で算出
・建物面積の価格相場は平均建物面積(坪数)×坪単価で算出
全国的な注文住宅の建物面積から見る価格相場は2,500万〜3,000万円で、平均住宅面積は36坪〜37坪です。
ローコスト住宅を実現するには、どのような工夫が必要なのか、次の項目を見ていきましょう。
4つのコスト削減工夫
ローコスト住宅がコストを抑えるには、以下のような方法があります。
シンプルな形状にする
家の外観はシンプルな形状にするのが費用を抑えるコツです。
外壁の凹凸が多いと外壁や屋根の面積が増えて建築費が上がります。なるべく外壁の凹凸を減らして、正方形に近いような形を検討しましょう。
また、同じ敷地面積の家を建てるときは、平屋建てよりも二階建ての方が延床面積を低いコストで確保しやすくなります。
設備や内装を標準にする
注文住宅の内装や設備はオプションやオーダーメイドも選べて魅力的ですが、追加費用がかかります。
特に、浴室やキッチンの設備は、グレードによって倍以上の価格差があるケースも少なくありません。
予算をオーバーしないように標準仕様を採用し、追加料金がかかるものは極力避ける方向で検討しましょう。
施主支給を取り入れる
どうしてもこだわりたい部分があるところは、施主支給を行う方法もあります。
ローコスト住宅の施主支給とは、内装や設備を自分で直接用意して、施工会社に取り付けてもらう手段です。
ただし、施主支給を受け付けていない建築会社もあるため、事前に確認しておきましょう。
低価格のセミオーダー住宅を選ぶ
規格住宅・セミオーダー住宅は工事内容が決められており、フルオーダーに比べるとローコストに抑えられます。
建売住宅よりも選択肢が豊富であり、個性を出しつつ工期短縮やコストダウンが可能です。
ローコスト住宅の選び方
ローコスト住宅選びで失敗しないためには、以下のポイントを考慮しましょう。
ローコスト住宅の失敗しない選び方のポイント
| ☑︎基本の住宅性能 ☑︎アフターサービス ☑︎希望の間取りとデザイン ☑︎複数の建築会社を比較 |
日本が自然災害の多い国である点を考えると、耐震性や断熱性など基本の住宅性能がどれくらいの強度なのかを調べておかなくてはなりません。
また、住宅設備の標準仕様に不便さはないかなど、写真や図面ではわからない部分は見学会などに足を運び、実物を確認しましょう。
ローコスト住宅は建てた後も設備の交換や塗装の塗り替えなど、メンテナンスが必要となります。
住み始めてから問題が見つかったとき、建築会社から十分なサポートを受けられるかどうかをチェックしておくとスムーズです。
ローコストだからといって、すべてを妥協するのではなく、好みの間取りやデザインが選べるか、どこまでカスタマイズできるかを知っておきましょう。
基本プランがベースになりますが、選択肢が豊富な建築会社であれば予算内で希望を叶えられる可能性もあります。
建築会社を選ぶ際は、複数の建築会社を比較して、工事や施工品質を確認するのも大切です。
最低でも2社以上のメーカーを検討し、実際に担当者と話をしたり、資料を見たりして自分の希望にピッタリの建築会社を見つけましょう。
予算設定の方法
注文住宅の費用項目はそれぞれ「本体工事費」「付帯工事費」「諸費用」「土地代」の4つに分けられます。
割合としては本体工事費が約70%〜80%、付帯工事費が約15%〜20%、諸費用が約5%〜10%です。土地代は広さや地域によって大きく異なります。
たとえば、土地あり30坪で坪単価45万円、建築工事費用が1,350万円とした場合の予算設定は以下の通りです。
| 建築工事費 | 1,350万円 | |
| 建築工事費の内訳 | 本体工事費 | 1,080万円 (建築工事費の80%) |
| 付帯工事費 | 270万円 (建築工事費の20%) |
|
| 諸費用 | 135万円 (建築工事費の10%) |
|
上記のように土地を持っていると予算をすべて建物にかけられますが、土地代も含めると建物にかけられる予算が変わってきます。
土地代込みでローコスト住宅を考えている方は、本体工事費を1,050万〜1,400万円ほどに設定して予算を組むのがおすすめです。
土地代は駅の近くなど利便性の高い人気エリアは高額です。駅から少し離れた土地も視野に入れて、土地代と建物代のバランスを考えて予算を設定しましょう。
理想の間取り・設備の決め方
ローコスト住宅の間取りや設備は、コストを抑えつつ、快適に過ごせるように工夫をしましょう。
ローコスト住宅でできる間取りや設備の工夫として以下の5つが考えられます。
・シンプルな間取りにする
・部屋や収納スペースを多く作らない
・屋根の高さを抑える
・高価な設備を選ばない
・省エネルギーな住宅を選ぶ
複雑な間取りやデザイン、収納スペースは、材料の切り出しや取り付けに時間がかかったり、作業工程が増えたりしてコストが高くなりがちです。
どうしても収納を増やしたい方は、階段下のデッドスペースを活用するなど、無駄のない間取りとデザインにして建築費用を抑えましょう。
斜面が緩やかな屋根を選ぶと屋根の面積が少なくなり、建築費用やメンテナンス費用でコストダウンを期待できます。
ローコスト住宅では、法律上や安全性の面で最低限の設備が標準仕様として用意されています。予算を上げてまで高価な設備を選ぶ必要があるのかを考慮して検討しましょう。
冷暖房のエネルギー消費を抑えられる省エネルギーの住宅は光熱費の節約だけでなく、国や自治体の補助金制度を利用できて、トータルのコスト削減にも繋がります。
品質チェックの具体策
ローコスト住宅の品質をチェックするには、以下のポイントを確認しましょう。
ローコスト住宅の品質チェックリスト
| ☑︎建築会社の実績や口コミを調べる ☑︎実物を確認する ☑︎使用されている素材を調べる ☑︎住宅性能評価を調べる☑︎基本性能を確認する |
ローコスト住宅を検討する際は建築実績を確認し、過去の事例を参考にデザインや間取り、素材、設備などの具体的なイメージを掴むと失敗しにくくなります。
また、家を建てたお客さまの声から、品質や住み心地のヒントが得られて自分に合った住宅を見つけやすくなるので、口コミもチェックしておきましょう。
欠陥住宅をなくすために国が定めている「住宅性能評価」に申し込むと、施主の希望通りに設計されているかといった評価を調査できて、第三者の専門家による確認ができます。
耐震性・断熱性・気密性などの基本性能が低いと、光熱費の増加や安全面で懸念が生じるかもしれません。
ローコスト住宅を手がける建築会社の中には基本性能に力を入れているところもあるので、複数の建築会社を比較しましょう。
一般社団法人 住宅性能評価・表示協会「登録住宅性能評価機関の検索」
よくある疑問と回答
ローコスト住宅でよくある疑問にお答えします。
Q.ローコスト住宅は地震に耐えられる?
A.1981年6月以降に建築されたすべての建物に「新耐震基準」が義務付けられており、ローコスト住宅も同じように基準をクリアしています。
これまでも耐震基準は厳しく改正されてきており、現在の基準はより優れた性能が求められるため、ローコスト住宅の耐震性も問題ないでしょう。
建築会社によっては、地震による建物の損傷のしにくさを示す「耐震等級」を公開しています。性能をそれぞれ比較するのも良いかもしれません。
Q.ローコスト住宅は何年持つ?
A.ローコスト住宅は一般住宅と同様の耐久年数を持っており、適切なメンテナンスを行えば20年〜30年以上住み続けられます。
ローコスト住宅を少しでも長持ちさせるには、日当たりの悪い土地や風通しの悪い外構を避けるなど、土地や設計にもこだわるのも大切です。
Q.ローコスト住宅を購入するのは恥ずかしい?
A.インターネット検索をすると「ローコスト住宅に住むのは恥ずかしい」といった意見もあり、心配される方も多いです。
恥ずかしいと感じるかどうかは人それぞれですが、外観や内装デザインの選択肢が少ないと不安が残るかもしれません。
ローコスト住宅でもデザインが豊富だったり、細かくカスタマイズできたりするなど、ご自分に合ったハウスメーカーを検討し、少しでも不安を無くすようにしましょう。
住宅ローン審査のポイント
ローコスト住宅でも一般の新築と同じように住宅ローンを組めます。住宅ローン審査のポイントを以下にまとめました。
住宅ローン審査のポイントチェックリスト
| ☑︎自己資金を用意して借入希望額を最小限にとどめる ☑︎返済比率を低く抑える ☑︎他のローン返済を済ませる ☑︎借入前の転職・退職は避ける ☑︎ペアローン・連帯債務・連帯保証でローンを組む |
返済比率とは、年収に占める返済額の割合で、返済負担率とも呼ばれます。
自己資金を増やすと住宅ローンの借入金額が減って返済比率も低くなり、審査が通る可能性が上がります。
自己資金無しでも住宅ローンを組めますが、自己資金があると借入期間が短くなるなどのメリットがあるので、可能な限り自己資金を準備しましょう。
自己資金は住宅購入金額の1割〜2割が目安です。
クレジットカードの分割払いとリボ払い、教育ローン、自動車ローンも借入の一種として返済比率に含まれ、返済比率が高いとローン審査が通りにくくなります。
他に借入がある方は、返済を済ませて返済比率を低くしてから住宅ローンを検討しましょう。
借入額が大きくてローン審査が通らないときは、収入合算やぺアローンを組む方法で審査が通るかもしれません。
ペアローンとは、たとえば夫婦共働きでそれぞれ年収を得ている場合に、夫婦それぞれの名義で別々の住宅ローンを組む方法です。
ただし、夫婦で別々のローンを組むと事務手数料も審査も2回分になります。
夫婦の年収を合算して審査できる連帯債務か連帯保証を利用して、審査を通りやすくする方法も考えてみましょう。
着工から完成までの期間
ローコスト住宅の着工から完成までの期間を表にまとめました。
ローコスト住宅着工から完成までの流れと期間
| 工程 | 内容 | 期間 |
| 近隣への挨拶 | 近隣の方への配慮として挨拶をする | 1日 |
| 地鎮祭 | 工事の安全を祈願するために行われる儀式 | 1日 |
| 基礎工事 | 建物を支える基礎を作る工程 | 約1ヶ月 |
| 上棟 | 建物の骨組みを組み立てる工程 | 約1週間 |
| 木工事・仕上げ工事 | 内装や外装を作る工程 | 1〜3ヶ月 |
| 内装・外装仕上げ工事 | 最終的な仕上げ作業 | 約1ヶ月 |
| 竣工検査・引き渡し | 完成後の検査と所有者への引き渡し | 1〜2週間 |
一般的な注文住宅の着工から完成までの期間は6〜12ヶ月ですが、ローコスト住宅はその半分の3〜6ヶ月と短い工期で済みます。
標準仕様を変更したり、デザインや設備にこだわったりすると工事の期間も伸びますが、希望が反映された標準仕様を選ぶと入居までの期間を短くできるでしょう。
お子さまの入学に合わせて引越したいなど、スケジュールに余裕がない方には大きなメリットになります。
まとめ:賢いローコスト住宅の選び方
この記事でご紹介したローコスト住宅を選ぶ際の具体的なポイントを下記にまとめました。
ローコスト住宅を選ぶ際の具体的なポイント
| ・シミュレーションした予算内で建てられるか ・広さや間取りは十分か ・希望条件を叶えられるか ・標準仕様の住宅性能とエネルギー効率は高いか ・建築会社の過去の実績や口コミはどうか ・アフターサービスの保証内容はどうか ・複数の建築会社を比較する |
賢くローコスト住宅を選ぶには、予算内で必要な機能を満たし、コストパフォーマンスを重視するのがポイントです。
また、ローコスト住宅の建築会社を選ぶときは、安く建てられる理由や住宅性能の確認をすると、建築会社の信頼性にも繋がります。
成功へのステップ
ローコスト住宅を建てるには、予算内で最大限の満足を得るための計画が重要です。
ローコスト住宅を成功させる手順とポイントを下記にまとめました。
ローコスト住宅購入成功へのステップ
| ステップ | ポイント |
| 1.総予算を立てる | ・月々の返済額まで考慮する ・超えてはいけない金額を設定する |
| 2.こだわりのある箇所を絞る | ・費用をかける部分とかけない部分を明確にする ・それ以外の部分は標準仕様にする |
| 3.コストを抑える方法を知る | ・家の形や間取り、設備などコストダウンできる部分を知って効率よくカットする ・形や面積など大きな金額を下げられる部分をよく調べる |
| 4.ローコスト住宅を建てられる建築会社を調べる | ・複数の建築会社に見積もりを出してもらう ・標準仕様を実際に見て決める |
| 5.建築会社の設計士に相談する | ・見積もりをさらに安くする方法を相談する ・他の業者で迷っていると伝える |
| 6.DIYや施主支給の方がやすくなる設備を削る | ・照明やエアコン、カーテンの取り付けは工事付きの他業者に頼む方法もある ・自分でできる作業は残しておいてもらう |
| 7.追加費用なく工事ができることを確認後に契約する | ・契約後の変更は高額になるため、追加費用なく希望通りの家が建つかを確認する ・階段の傾斜やキッチンの高さなど、細かい部分は実物をみてシミュレーションする |
価格を抑えるのに少し手間のかかる部分もありますが、なるべく追加費用がかからないように工夫しながら以上のステップを実行し、ローコスト住宅の購入を成功させましょう。
家づくりのご相談は”豊栄建設”へ
札幌市にある住宅建築会社「豊栄建設」では、高断熱・高気密な家づくりや、地震に強い家づくりに取り組んでおり、安全性能や快適性能に高い評価を得ています。
豊栄建設の住宅の中でも代表的なのが「価格」「品質」「サポート」という3つのキーワードをテーマにした「チャレンジ999」です。
建築材料を取り扱うグローバル企業の「LIXIL」と共同開発した高性能ウレタンパネルで35年の無結露保証を実現し、北海道の冬の積雪や厳しい寒さにも耐えられる、あたたかい住まいを1,000万円代から提供しています。
豊栄建設では、各分野のプロフェッショナルがチーム体制で相談からアフターサポートまで一貫して対応しており、お客様の要望をしっかりと汲み取ってくれます。
高断熱・高気密なローコスト住宅を検討している方は、ぜひ豊栄建設にご相談ください。
まとめ
ローコスト住宅が価格を安く抑えられる理由は材料の統一、プランの規格化、人件費の削減などが挙げられ、完成までのスピード感やこだわりたいところに予算をかけられるなどのメリットがあります。
しかし、同じローコスト住宅でも建築会社によって予算内で実現できる設備や住宅性能、保証期間、アフターサービスに差があります。
設備や素材のグレードが高くなくても、地域の気候に合わせて適切な断熱性・気密性を提供しているような建設会社であれば失敗しにくいでしょう。
まずは見積もりの検討からはじめ、プランや金額が明確か、自由度はどれくらいか、具体的な提案を出してくれるかなど、複数の建築会社を検討しましょう。
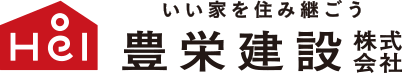


 お客様相談室
お客様相談室 資料請求
資料請求


 見学ご予約
見学ご予約


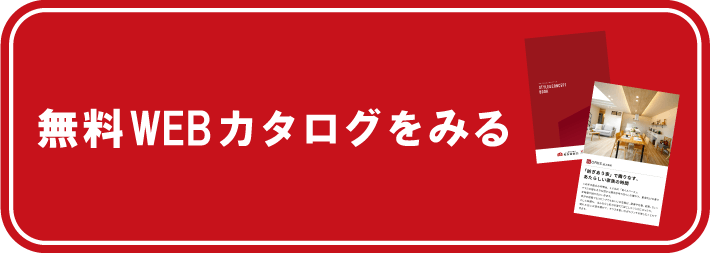
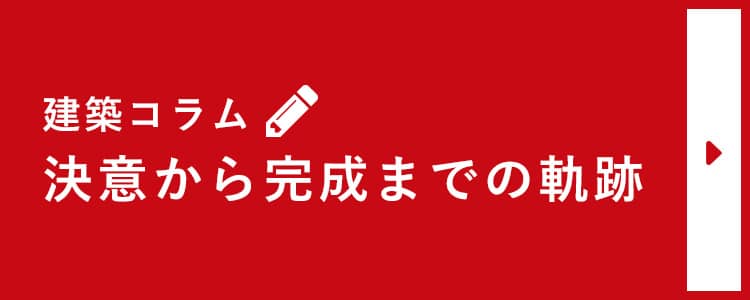







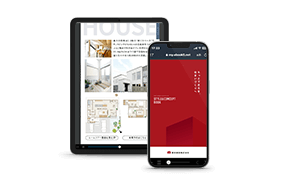




 Facebook
Facebook LINE
LINE Instagram
Instagram YouTube
YouTube

