セミオーダー住宅の真実!【2025年版】プロが教える選び方7つのポイント

注文住宅にはフルオーダーとセミオーダーの2種類があり、ある程度間取りや設備が決められているセミオーダー住宅は、スムーズに進められてコストも抑えられるのが魅力です。
しかし「セミオーダーだと希望が叶えられないのでは?」「各社商品の違いがイマイチよくわからない」と悩む方も少なくありません。
そこで、この記事では失敗しないセミオーダー住宅の選び方や注文住宅と規格住宅のメリット・デメリット、注文住宅・規格住宅が向いている人などを紹介します。
これから注文住宅を検討する方はぜひ参考にしてください。
注文住宅・規格住宅の選び方完全ガイド
住宅選びの主な基準として「予算・土地条件・家族構成・ライフスタイル・将来計画」が挙げられます。
たとえば、予算は年収から負担可能な金額を計算していくと、建てられる住宅の予算がわかり、予算オーバーといったリスクを回避できるのです。
【年収からみる予算例(返済負担率20〜30%)】
・3,000万円以下:年収380万〜500万円
・3,000万〜4,000万円:年収400〜600万円
・4,000万円以上:年収670万円〜800万円
土地条件は住まいの利便性を左右する重要なポイントです。具体的な判断基準は以下のようなものがあります。
【土地条件の判断基準】
・通勤・通学の利便性
・周辺の商業施設の多さ
・治安、子育て環境
・都市計画など将来的な住環境の変化
住宅の間取りや広さを検討するときには、家族構成が基準となります。家族人数別の間取りの目安をみていきましょう。
【家族構成から見る間取りの基準】
・3人家族:子ども部屋+夫婦の寝室+リビングで2LDK以上
・4人家族:子ども部屋2+夫婦の寝室+リビングで3LDK以上
・6人家族:子ども部屋2〜4+夫婦の寝室+リビングで3〜5LDK以上
在宅勤務が多く仕事部屋が必要な方や、朝が早いから駅の近くが便利な方など、ライフスタイルも住宅選びのポイントになります。
【ライフスタイル別の選び方】
・組織に属さないフリーランスの方:自宅兼事務所となる間取りや広さにする
・自然に囲まれて暮らしたい方:都市部から離れた閑静な住宅街に建てる
・交通アクセスなど利便性の高い地域に暮らしたい方:駅の近くや都市部に近い土地を選ぶ
住宅選びでは将来を見据えて、以下のポイントも考慮しましょう。
【将来計画のポイント】
・結婚、妊娠、進学などライフステージの変化を予測する
・月々のローン返済負担額や生活費用とのバランスなど経済的な収支を立てる
・耐久性・耐震性など住宅基本性能を重視する
・経年劣化によるメンテナンス費用も考える
このように、住みやすさと安心を得るには、生活スタイルの変化を見越した計画的な住宅選びが求められます。経済的な負担を軽減しながら、変化に柔軟に対応できる家づくりを目指しましょう。
セミオーダー住宅の特徴と選び方
セミオーダー住宅は規格住宅とも呼ばれており、フルオーダーの注文住宅には及ばないものの、コストを抑えつつ、ある程度は自分好みにできるのが魅力です。
セミオーダー住宅の特徴をまとめました。
【特徴】
・基本的な間取りや設備が決められていて、建築コストを抑えられる
・工期が短く、転職や入学など入居を急いでいる方にも向いている
・フルオーダー住宅よりも打ち合わせ回数が少なく、施工主負担が少ない
・こだわりたいところに予算をかけられる
フルオーダー住宅とセミオーダー住宅の違いを表で比較してみましょう。
| 価格帯 (土地購入資金を除く) |
工期 (着工から完成まで) |
カスタマイズ範囲 | |
| フルオーダー住宅 | 4,319万円 | 3〜4ヶ月 |
・間取り |
| セミオーダー住宅 |
2,700万円 |
2〜3ヶ月 |
・間取り |
| 建売住宅 | 2,361万円 | 4ヶ月程度 | カスタマイズできない |
参照:国土交通省「令和5年度住宅市場動向調査報告書」PDF121ページより
・建売住宅は建売住宅購入資金から土地購入資金1,929万円を引いて算出
参考:豊栄建設「標準仕様38.875坪ベストチョイス4LDK」より
セミオーダー住宅の代表的なハウスメーカー3社を紹介します。
ダイワハウス「スマートデザイン」】
ダイワハウスのセミオーダー住宅はスマートデザインと呼ばれ、以下のような特徴があります。
・平屋か二階建てを選べる
・1,000通り以上の間取りからカスタマイズできる
・フルオーダー同等の大空間も実現可能
【ヘーベルハウス「my DESSIN」】
ヘーベルハウスのセミオーダー住宅はmy DESSIN(マイデッサン)と呼ばれ、特徴は以下の3つです。
・買取保証があり将来も安心できる
・プロが厳選した誰もが使いやすい間取りから選べる
・スマートミーティングで打ち合わせ時間と手間を短縮できる
【住友林業「フォレストセレクションBF」】
住友林業のセミオーダー住宅はフォレストセレクションBF(ビーエフ)と呼ばれ、以下のような特徴があります。
・住友林業ならではのオリジナル木材が選べる
・天井や窓もカスタマイズ可能
・ホームページの間取りシミュレーションから理想の間取りがつくれる
ご紹介したように、セミオーダー住宅はハウスメーカーによってさまざまなカスタマイズ方法や豊富なデザインがあるため、複数のメーカーを比較して検討するのがおすすめです。
失敗しないセミオーダー住宅の選び方
セミオーダー住宅を選定する重要なポイントは、以下の5つです。
【選び方】
・標準仕様の範囲を確認する
・オプション料金を把握する
・標準仕様の実物をチェックする
・保証期間やメンテナンス体制などアフターサービスを確かめる
・施工実績で選ぶ
セミオーダー住宅のよくある失敗事例と対策を紹介します。
【失敗事例】
・土地条件による失敗例:変形地や狭小地など特殊な土地では制限があり建築できない
・間取りの設計に関する失敗例:吹き抜けを設けた結果、2階が狭くなった
・設備に関する失敗例:キッチンが身長に合わなくて不便になった
上記の失敗事例に対する対策としては以下のようなものがあります。
【対策】
・変形・狭小地など特殊な敷地では、事前に建築可否や快適な住環境が実現できるかを確認する
・コンパクトな部分吹き抜けや吹き抜けをつくらずにお部屋の開放感やデザイン性を高める方法を採用する
・ショールームなどを訪問し、実際に料理をする姿勢で無理がかからないかチェックする
セミオーダー住宅は家づくりのプロが用意したプランから選ぶので、失敗を避けられるのが魅力ですが、土地条件やこだわりの強さによっては満足できない可能性もあると考えておきましょう。
住宅ローンと資金計画の基礎知識
資金計画を立てるうえで最初に決めるのは「頭金」と「ローン借入額」「月々の返済額」「諸費用」の4つです。
注文住宅と規格住宅の一般的な資金計画をまとめました。
注文住宅の資金計画例
| 住宅購入費用 | 4,300万円 | |
| 資金計画 |
頭金 |
860万円 |
| ローン借入額 | 3,000万円 | |
|
月々の返済額 |
月々7万6,229円 | |
|
諸費用 |
430万円 | |
規格住宅の資金計画例
| 住宅購入費用 | 2,700万円 | |
| 資金計画 |
頭金 |
540万円 |
| ローン借入額 | 1,900万円 | |
|
月々の返済額 |
月々4万8,278円 | |
|
諸費用 |
270万円 | |
諸費用の内訳は以下の通りです。
諸費用の種類と内訳
| 諸費用の種類 | 内訳 |
| 仲介手数料 | 「購入価格×3%+6万円」が上限 |
| 事務手数料 | 10万〜20万円 |
| 不動産取得税 | 購入価格の3%(軽減税率適用) |
| 契約書の収入印紙代 | 1万円(1,000万円超え5,000万円以下軽減税率適用) |
| 所有権保存登記費用 | 1.5万円〜3万円 |
| 測量費用 | 30万〜60万円 |
| 建物表題登記の費用 | 5,000円〜1万円 |
| 火災保険料・地震保険料・団体信用生命保険料 | 4〜6万円 |
| 住宅ローン関連の費用 | 10万〜20万円 |
住宅ローンの種類は以下のようなものがあります。
|
【固定金利】 【変動金利】 【長期固定金利住宅ローン「フラット35」】 |
住宅ローンを選ぶときは、金利タイプや返済方法、相談のしやすさなどを考えて比較し、検討しましょう。
設計自由度とコストで考える!注文住宅と規格住宅
理想を形にできる「フルオーダー・セミオーダー住宅」
フルオーダー住宅とセミオーダー住宅の違いを表にまとめました。
| セミオーダー住宅 | フルオーダー住宅 |
|
・コストを抑えられる |
・こだわりをすべて反映できる |
フルオーダー住宅とセミオーダー住宅の両方を扱う北海道の建設会社「豊栄建設」の実例をご紹介します。
【フルオーダー:完全自由設計の和モダン住宅】
|
・施工主のこだわり:和の趣を感じる畳スペースのあるリビングや小上がりがホッと安らげる場所の設計にこだわりました。 ・施工ポイント:リビングや寝室の前に小上がりスペース、2階に広がるバルコニー、全館冷暖房、外観 |
【セミオーダー:標準プランをベースにした北欧テイストの住宅】
|
・施工主のこだわり:床の一部に高低差をつけて1.5階や2.5階とスキップフロアのあるお家。壁紙やインテリアなどは奥様が希望されたフィンランドテイスト。食器棚は奥様手作りの施工主支給で費用を抑えています。 ・施工ポイント:スキップフロア、壁紙、床暖房、ビルトインガレージ |
フルオーダー住宅は自由度が高いため好きなように設計できて理想的ですが、セミオーダー住宅もこだわりたい部分を絞ると希望の間取りやデザインを取り入れることができるとわかります。
コストパフォーマンスに優れた「規格住宅」
規格住宅とはハウスメーカーや工務店があらかじめ用意した「規格」に基づいて建てる住宅のこと。資材やデザインはカタログから選択して決めていきます。内装や設備だけでなく、間取りや外観、屋根などの住宅の構成要素も選択肢の中から組み合わせて、どのような住宅にするのかを設計します。基本的に規格外の間取りは選べず、パーツの配置変更もできません。自由度は下がるもののコストは抑えられるため、コストパフォーマンスに優れた住宅だといえます。
近年は規格住宅を提供する企業が増えており、洗練されたデザインの住宅も増加中。ひとつの企業だけではなく、さまざまな企業の規格をチェックすることで好みのデザインを見つけられるでしょう。
注文住宅と規格住宅の違いを比較表で解説
注文住宅と規格住宅の違いは設計の自由度やコストだけでなく建築期間、メンテナンス性などがあります。
| 比較項目 | 注文住宅 | 規格住宅 |
| 設計自由度 | 基本的にすべてを自由にカスタマイズできる | 間取りや内装、設備などの一部をカスタマイズ可能 |
| コスト | 自由に設計できる分、高くなりやすい | フルオーダーに比べると費用を抑えられる |
| 工期 | パターン化されていないため長期間になりやすい | 建築方法がパターン化されていて比較的短い |
| メンテナンス性 | 断熱性・気密性・耐久性などが高い建材を選べてメンテナンスコストを削減できる | 標準仕様の建材はグレードが低い可能性もあり、一般的な経年劣化に伴いメンテナンスが必要になる |
| 将来の資産価値 | 耐久性や快適性などから、規格住宅よりも将来の資産価値は高い | 標準仕様の建材だと約30年ほどで建物の価値がないとされるが、低コストな分、子供が独立してから新たに建て直す方法もある |
注文住宅の方が将来の資産価値や耐久性の高さから優位に見えますが、初期コスト面や工期を見ると規格住宅も優れているとわかります。
注文住宅のメリット・デメリットとは?
注文住宅のメリット
外観・内装にこだわれる自由度の高さ
注文住宅の最大の魅力は自由度が高く、理想の家が建てられる点にあります。外観や内装・間取り・構造・素材など細部までこだわることができるため、希望に沿った家の実現が可能。吹き抜けの玄関・広いリビング・デザイン性のあるキッチンなどの理想を形にできます。
デザインだけでなく、耐震性能・機密性・断熱性能といった機能性を重視し、安心して長く住める住宅の完成に向けて力を注ぐことも可能。建築の専門知識がない人であっても工務店・ハウスメーカーの担当者が相談に乗り、一緒にこだわりを実現する方法を考えてくれます。住宅に対する理想やこだわりがある人にとっては大きなメリットだといえるでしょう。
土地選びからこだわれる
注文住宅では、土地選びの段階から自分や家族のライフスタイルに合わせたこだわりが反映できます。
例えば通勤や通学の利便性を重視する場合、駅や幹線道路までの距離が近い場所の土地を選択できます。住環境で選ぶなら、閑静な住宅街や自然豊かな郊外のような静かなエリアか商業施設や病院などに近い便利なエリアといった選択が考えられます。また、子育てや介護のサポートが手厚い自治体を基準にした土地選びも可能です。
土地を選ぶ際には、どんなエリアに住みたいかだけでなく周辺地域の開発計画を確認し、将来的な住環境までイメージすることで住宅完成後の満足度も高められるでしょう。
建築過程を確認できる安心感
注文住宅における「施工品質の確認方法」には以下のようなものがあります。
【施工品質の確認方法】
・竣工検査:施主立ち会いの検査で、施工時の不具合や不備がないかを確認する検査
・建築確認検査:建築会社が国が定めている建築基準法に基づいて行う検査
・住宅瑕疵保険による検査:住宅瑕疵保険法人による検査
・住宅性能評価による検査:施工会社が依頼する検査
・フラット35適合証明による検査:施工会社が依頼する検査
・第三者機関による検査:住宅の施工品質を詳細に検査
上記の中でも住宅瑕疵保険は将来のメンテナンス時に役立ちます。
新築の住宅を引き渡す施工会社は「瑕疵担保責任保険」への加入を義務付けられており、万が一施工会社が倒産してしまっても、10年間の「主要構造部の欠陥と雨漏り」の保証は担保されるのです。
将来の増築にも対応しやすい
注文住宅は将来の増築やリフォームなどの変化に柔軟に対応できる設計が可能です。
目的に応じた増築アイデアの具体例として以下のようなものが挙げられます。
・子供部屋の追加:将来的に独立を見据えて、部屋を仕切れるような設計にする
・親の介護スペース:親世代の生活動線やバリアフリー化、部屋数を増やせるような設計
・在宅ワークスペース:テレワーク対応の静かな書斎や収納を充実させる
しかし、増築は周囲にも影響を及ぼすリスクがあり、次のような構造上の理解と配慮が必要不可欠です。
【建ぺい率・容積率の上限】
・建ぺい率とは敷地面積に対する建物面積の割合、容積率は敷地に対する延床面積の割合を指し、地域で指定された上限を超えての増築はできません。
【再建築不可】
建築基準法第43条に定められた接道義務(幅員4m以上の道路に2m以上接していること)を果たしていない建物を再建築不可物件と呼び、増築も原則不可となっています。
【自治体の条例による制限】
景観を維持するための風致地区や地域の発展を抑える市街化区域、住宅地の日照を守る斜線規制など、自治体で決められたさまざまな制限をクリアする必要があります。
制限や上限に関しては設計者の方と相談しながら、将来を見据えて増築を検討すると、長く快適に過ごせるでしょう。
注文住宅のデメリット
住宅完成・入居までに時間が掛かる
希望に沿った家を建てるためには、間取りや外観、設備、素材など、決めるべき内容が必然的に増えてしまうもの。何度も打ち合わせを行う必要があり、契約までには通常1~2ヶ月以上の期間がかかります。
土地探しから始める場合には、理想の土地が見つかるまでの時間もかかり、探している間は住宅の設計を進めることもできません。入居まで短く見積もって半年、長い場合には1年以上かかることも。注文住宅を選ぶなら、希望の入居時期に合わせて時間的に余裕のある計画を立てるようにしましょう。
規格住宅と比べてコストが高い
依頼主の好みやニーズに合わせて、自由にカスタマイズできるのが注文住宅の魅力。一方で、その自由度の高さが建築コストの増加に繋がります。予算を決めた状態で家づくりの打ち合わせを始めた場合でも、話し合いながら希望が膨らみ、細かなこだわりの積み重ねによって予算オーバーするケースも少なくありません。特殊な資材・設備を用いた場合は、建築時だけでなく高額なメンテナンス費用も発生する可能性があります。規格住宅の場合はできる範囲が決まっている分、建築コスト・メンテナンス費用が予算内に収めやすいといえるでしょう。
注文住宅では、予期せぬ費用増加に備えるためにも余裕のある予算設定が大切です。適切な予算管理をするためには、住宅に取り入れたい内容の明確化がおすすめ。こだわりたい部分・こだわらない部分を決めることで、コストを抑えつつも理想の住宅を実現できるでしょう。
完成イメージが分かりにくい注文住宅の対策
自由に設計できるのが魅力ですが、自分が設計を考えた住宅は完成イメージが分かりにくいので、完成するまで安心できないと悩む方も多いです。
完成イメージで悩んだ時の対策として以下が挙げられます。
・完成イメージが立体的に見られるシミュレーションソフト「3Dパース」を使ってさまざまな角度からチェックする
・仮想空間を現実のように体験できるVR(バーチャルリアリティ)によって完成イメージの内装・外観を体感する
・モデルハウスを見学したり、施工事例をたくさん見たりして住まいのイメージを持っておく
3DパースやVRは、モデルハウスの見学と違って時間や場所に縛られず、いつでも内覧できる点がメリットと言えるでしょう。
しかし、3DパースやVRによる内覧は映像と感覚がズレて、具体的な距離感・広さが掴めないといったデメリットもあります。
より詳しく建物の広さや距離を把握したい場合は、モデルハウスまで足を運んで、自分の設計に近い間取りを確認するのがおすすめです。
注文住宅が向いている人とは?
国土交通省「令和5年度住宅市場動向調査報告書」より注文住宅に向いている人の具体的な例をまとめました。
|
家族構成:子ども1+夫婦の3人家族 |
参照:国土交通省「令和5年度住宅市場動向調査報告書」PDF116ページより
こんな人におすすめ
| おすすめな人 | 特徴 |
| デザイン重視派 |
・壁紙などのデザインだけでなく、テイストや空間構造、仕上げ方法など、すべてにおいてこだわりたい |
| 高性能住宅志向派 | ・耐震性・耐久性だけでなく、冷暖房のエネルギー消費を抑えられる断熱性能や気密性を重視したい |
| 将来の変化に備えたい人 |
・将来を考えて二世帯で住めるように間取りを工夫したり、バリアフリー対応にしたりしたい |
コストをかけられる方は、さまざまなリスクや将来性に対応できる注文住宅を選ぶと満足できるでしょう。
規格住宅のメリット・デメリットとは?
規格住宅のメリット
工期が短いため入居までがスムーズ
規格住宅の打ち合わせはカタログから比較検討して選択するため、注文住宅と比べてやり取りの回数・時間が少なくて済みます。打ち合わせがストレスに感じる人でも、精神的な負担が軽減され、楽しみながら家づくりを進められるでしょう。
規格住宅の建材は規格化されたものを工場であらかじめ加工し、現場へ持ち込み建設します。建築工程がマニュアル化されており、施工がスムーズに進められるため工期が短縮できるだけでなく、建築中の住宅が風雨などに晒されるリスクも抑えられます。
家づくりに掛けられる時間が決まっている場合、規格住宅は魅力的な選択肢のひとつになるでしょう。
建築コストを抑えられる
規格住宅は建材や工法が規格化されているため、注文住宅と比較して建築コストを抑えられます。品質を落として低価格を実現しているのではなく、設計の自由度が低いぶん使用する材料が限定的で、大量生産された材料を使用し、画一化された作業ができるため材料費を抑えられるのです。
また、工程のマニュアル化による短い工期が人件費の削減に繋がっています。カスタマイズできる範囲が限られ、規格化されているからこそ低価格・高品質な住まいを建てられるのです。
建築費用が分かりやすく確定も早い
規格住宅は選択するプランに応じて建築費用の目安が記載されているため、特別な依頼をしない限り建築費用に大幅なズレは生じません。坪数と坪単価費用を計算し、建築費用を早いタイミングで確定できます。
発生する費用に目途が立つことで、資金面において安心感を持ちつつ家づくりを進められるでしょう。
間取りや仕様を決めやすい
規格住宅はハウスメーカーや工務店が用意した基準に基づいて設計・建築されるため、間取りや仕様を一から考える必要がありません。
注文住宅は自由度が高い分、細かい部分まで決定する必要があり、選択の幅が広すぎることで多くの打ち合わせが発生。理想を形にする作業を負担に感じて後悔するケースもありますが、規格住宅の設計はあらかじめ用意されたカタログの中から選ぶため、自ら考える負担を抑えつつ間取りや仕様を決められます。
具体的な理想・こだわりポイントが少ない場合には、規格があることで自身の生活にイメージを落とし込みやすくなり、失敗を避けた家づくりができるでしょう。
完成をイメージがしやすく、後悔しにくい
規格住宅はデザインや間取りがあらかじめ決まっているため、完成後のイメージがしやすく、想像と違った…と後悔するリスクを抑えられます。
ハウスメーカーや工務店の経験とノウハウが反映された間取りを選べるため、機能性や暮らしやすさを保ちつつ、自分のライフスタイルに合った住宅を手に入れられるでしょう。
規格住宅のデメリット
間取り・仕様変更の自由度が低い
あらかじめ設定された仕様から選ぶ規格住宅はオリジナリティのある間取りや仕様の変更が難しく、理想を叶えられない可能性があります。
カスタマイズ・オプションのバリエーションが豊かな規格住宅もあるため、こだわりたいポイントがある場合は理想に近い設計・仕様を提供している業者を選ぶとよいでしょう。
土地の形状・広さによっては建てられないケースもある
規格住宅は一般的な宅地の形状や広さを前提に設計されているため、特殊な形状(三角地・台形地・狭小地など)の土地や高低差のある土地では建築ができない場合があります。間口が狭い土地や、防火地域など規制が厳しい土地では、標準的な建材やプランでは対応できない可能性も。土地の購入から検討している場合には、事前に住宅会社へ相談するとよいでしょう。
土地の形状に合わせたカスタマイズやアレンジができる業者もあるため、柔軟な対応をしてくれる業者を探しましょう。
規格以外の設備を選ぶとコストが割高になる
規格住宅では、同一仕様の製品を大量発注することで単価を下げ、低コストを実現しています。そのため、標準仕様以外の設備を選ぶと個別発注する費用があり、大量発注のメリットを受けられません。こだわりたい場所・範囲が増えるにつれ、標準仕様と比べてコストが割高になっていきます。
規格住宅を建てる際には自分の理想と予算を照らし合わせ、標準仕様の設備で満足できるか、追加コストを払ってでもカスタマイズを施したいか十分に検討しましょう。
規格住宅が向いている人とは?
こんな人におすすめ
| おすすめな人 | 特徴 |
| 共働き夫婦 |
・予算や時間を重視している |
| 子育て世代 |
・子どもの入園・入学に合わせて、入居時期のタイミングを決めたい |
| 定年後の夫婦 |
・築年数の経った自宅だと耐久性が心配になる |
表にあるおすすめな人で、それぞれの規格住宅の選び方をまとめました。
・共働き夫婦は日常生活も忙しいことが多いので、家事の時間を短縮できるようなスムーズな生活動線、収納スペースを意識して選ぶ
・子育て世代は子どもが室内で遊べる広々とした空間や大きくなってから使う子ども部屋、収納スペースなどを考えて選ぶ
・定年後の夫婦が規格住宅を選ぶ際はバリアフリーや間取り、広さについて考慮する
まとめ
フルオーダー住宅は細部まで自分好みにできる点が魅力で、セミオーダー住宅は仕様や間取りの一部を選べて、費用を抑えながら理想を叶えられるのがメリットと分かりました。
フルオーダー住宅とセミオーダー住宅は、どちらもメリット・デメリットがあるため、それぞれの特徴から、自分や家族のニーズに合っている住宅を選びましょう。
また、規格住宅はハウスメーカーによってカスタマイズの自由度が異なります。複数のハウスメーカーから自分のこだわりを叶えられるようなハウスメーカーを見つけましょう。
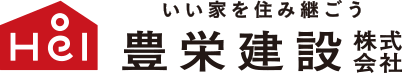


 お客様相談室
お客様相談室 資料請求
資料請求


 見学ご予約
見学ご予約


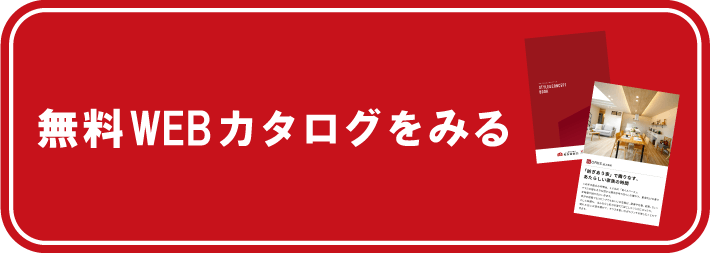
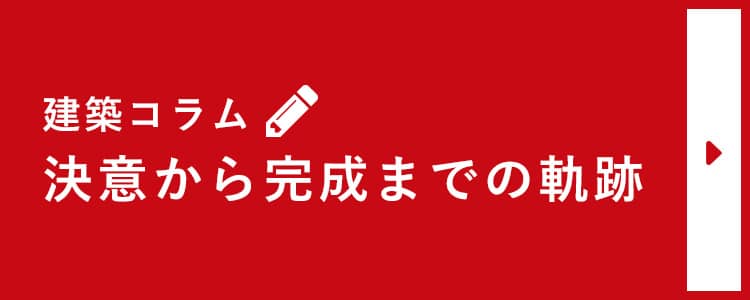







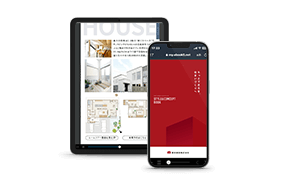




 Facebook
Facebook LINE
LINE Instagram
Instagram YouTube
YouTube

